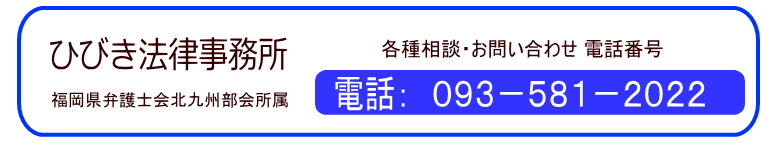会社や企業が労働者を雇用する場合、特に雇用期間を設けずに採用する場合もあれば、雇用期間を定めて、労働者を採用する場合もあります。
会社や企業が労働者を雇用する場合、特に雇用期間を設けずに採用する場合もあれば、雇用期間を定めて、労働者を採用する場合もあります。
後者の場合は、たとえば、雇用期間を1年としたり、3年としたり、といったケースです。
このように、雇用に際して、契約で雇用期間を定めた雇用契約を有期雇用契約といいます。
本記事は、この有期雇用契約の期間満了と更新をテーマにした記事です。
有期雇用契約における契約期間の満了と更新
この優雇用契約に関しまず、契約期間満了の効果と、契約の更新について確認します。
契約期間満了の効果
有期雇用契約においては、契約の期間満了とともに、労働契約は終了します。
たとえば、ある年度の4月1日から翌年の3月31日までを雇用期間とした場合、同3月31日満了時点で、雇用契約に終期を定めた効果として雇用契約は終了します。
契約成立時の合意の効果として、労働契約が終了する訳です。
更新
もっとも、期間を定めた雇用契約は、当然、当事者間の合意により更新することが可能です。
更新に際しては同一条件で更新する合意書が作成されたり、賃金条件などの条件が変更を前提に更新される場合もあります。
他方、中小企業に少なくないのですが、新たに合意書等は作成されず、黙示・暗黙の了解のもとで、労働契約が更新されることもあります。
民法629条1項について
 更新合意の有無を巡って問題となるのは、契約期間満了後、労働者が引き続き就労を続けていたのに、後になって、使用者側が期間満了による労働契約の終了を主張するケースです。
更新合意の有無を巡って問題となるのは、契約期間満了後、労働者が引き続き就労を続けていたのに、後になって、使用者側が期間満了による労働契約の終了を主張するケースです。
上記のとおり、労働契約の更新が黙示で行われることも少なくない為、後になってトラブルが生じうるのです。
この点に関しては、民法629条1項が手当となる規定を置いています。
民法629条1項による手当
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。
この規定によれば、期間満了後、労働者が就労を続け、使用者側がこれを知りながら異議を述べなかった場合、民法629条1項により、労使間において、黙示に更新の合意があったことが推定されます。
そのため、この場合、使用者側で黙示の合意があるとの推定を覆す立証ができない限り、裁判では黙示の更新合意があったものと扱われます。
民法629条1項前段の「同一条件」
民法629条1項前段が適用される場合、従前の雇用と「同一の条件」で更に雇用をしたとの取扱いになります。
この「同一の条件」というのは、賃金や労働時間等の諸条件が従前の有期労働契約と同一であることを意味しますが、更新後の「契約期間」については、議論があります。
<無期契約になるとの見解>
ここで、民法629条1項後段を再度ご確認いただきたいのですが、同1項後段は、「この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。」と定めています。
この民法627条は、期間の定めのない労働契約の解約(解雇)に関する規定です。
そこで、学説の一つは、期間の定めのない労働契約関する民法627条の規定によるとされている以上、民法627条1項前段の規定にて更新された場合には、当該雇用契約は期間の定めのない労働契約になる、との立場をとっています。
この見解によれば、先に挙げた1年の有期雇用契約の例で、民法629条1項前段を適用すると、更新後は、契約期間の定めのない労働契約(無期契約)になります。
<有期契約のままであるとの見解>
他方、もう一つの見解は、民法629条1項前段が定める「同一の条件」という文言を重視して、「期間」も同一のはずだ、という見解です。
この見解によると、上記1年の有期雇用契約の例で、民法629条1項前段を適用すると、更新後の契約期間も1年ということになります。
両見解の差異
上記民法629条の議論は、無期契約になるのか、有期契約になるのか、との点で結論に大きな差異が生じさせ得ます。
無期と有期とでは、労使の長期継続性が予定されるのか否かにが根本的にことなりますし、法の適用上も、たとえば、前者であれば、使用者の解雇につき労働契約法第16条が適用となるのに対して、後者であれば、その解雇につき、同法17条が適用となります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
<労働契約法17条1項>
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
この点に関し、裁判例では、有期とする結論をとるものもあれば、無期とする結論をとるものもあります。
裁判例は、上記いずれかの見解に組すると言うよりは、民法629条1項は、推定規定なのだから、労働期間について諸事情を考慮の上、実体に則した合意内容を模索する方法で、具体的な解決が志向されているように思います。
あるいは、無期とする見解を取ったうえで、労働期間につき、推定覆滅を緩やかに認めているのかもしれません。
そうだとすれば、いずれにしても、上記学説の対立に拘泥することにそれほど意味はなく、期間満了後に勤務を継続していた労働者及びこれに異議をとどめなかった使用者の意思を探求していくことが重要になります。