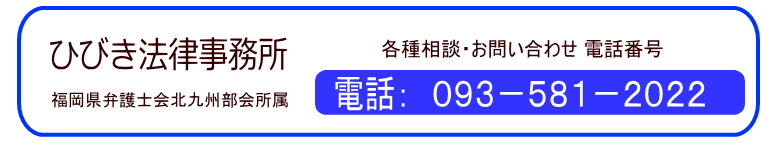労働者が労働中の事故や業務に起因する傷病を負って休業せざるをえなくなることは往々にしてありえます。
たとえば、労働中の事故の例としては、工場で製品を製造する過程で発生する事故や、従業員が自動車を使用して営業に回る際に発生する事故などが考えられます。
また、業務に起因してうつなどの精神疾患が発生する、といったケースも考えらます。
今回のテーマは、こうした労働中の事故や業務に起因する傷病によって休業している従業員の解雇や退職についてです。
なお、以下、便宜のため「労働中の事故や業務に起因する傷病」のことを、「業務起因性のある傷病」といいます。
法律による解雇権の制限
労働基準法19条1項本文は、業務起因性のある傷病によって休業している従業員を解雇することにつき、次のように定めています。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
この規定は、使用者たる会社等が、次の①及び②の労働者につき、休業期間中及びその後の30日の間に解雇をすることを禁止した規定です。
① 業務上負傷し、または疾病にかかって休業する労働者
② 産前産後に休業する女性労働者
会社が、業務起因性のある傷病によって休業した労働者(上記①の労働者)を対象に、当該休業期間中またはその後30日の間に行った解雇は、この規定により無効となります。
就業規則にある休職期間後の退職
上記のとおり、労働基準法19条1項本文は、上記の通り、使用者の解雇を制限する規定です。
では、「解雇」ではなく、会社から「退職扱い」とされる場合にはどうでしょうか。
この点が問題となるのは、一定の休職期間満了後、休職事由が消滅していない場合に労働者を「退職扱い」とする規定が就業規則に設けられていることが少なくないからです。
この点、確かに、労働基準法19条1項は、「解雇」に関する規定ですので、「退職扱い」が直接、同条1項本文に反するとはいえないとも考えられます。
しかし、労働基準法19条1項本文は、業務起因性のある傷病を負った労働者等が安心して療養し得るように、当該労働者の地位を保証しようとした規定です。
それにもかかわらず、「解雇」でなく、「退職扱い」であれば労働者の地位を喪失させることも許される、と考えるのであれば、労働基準法19条1項本文の趣旨が損なわれてしまいます。
解雇はダメだが、退職扱いであればOKというのでは、この規定の趣旨・目的が達成できません。
そこで、就業規則に上記のような「退職扱い」の規定が設けられている場合であっても、これを根拠に退職扱いとすることは、やはり労働基準法19条1項本文の趣旨に反するものとして無効と解されます(同条1項の類推適用)
たとえば、大阪高等裁判所平成24年12月13日判決は、業務に起因する精神疾患のために2年間休職していた労働者を、休職期間満了をもって退職扱いとすることは、労働基準法19条1項の類推適用により、無効であるとしています。
打切補償
上記のとおり、労働基準法19条1項は、業務起因性のある傷病を負った労働者を休業期間中等に解雇することを厳しく制限しています。
もっとも、他方で、その但書は、一定の条件の下、労働基準用19条の解雇制限の解除を認めています。
具体的には、次の二つの場合です。これらに該当する場合、労働基準法19条1項の解雇権の制限は解除されます。
<解雇権制限が解除される二つの場合>
① 使用者が業務上の傷病について療養開始後3年を経過しても治らないため、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合
② 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合(主務官庁の認定を要する)
業務起因性のある傷病により休業中の労働者を解雇ないし退職扱いとしようとする場合には、上記①又は②の条件を満たさなければなりません。
なお、上記①及び②のうち、会社の事業継続を前提とした場合、会社が取りうる選択肢は、①1200日分の賃金の補償のみとなります。
そして、1200日分という賃金の額は、会社にとっても決して軽々な判断ではなしえるものではありません。
同但書は、会社に選択肢は与えているものの、その反面、法が労働者の地位を相当高度に保証しようとしていることを窺わせるものともいえます。
労働基準法19条1項本文の再掲を含め、関連条文を上げておきます。
労働基準法第19条
第1項
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
第2項
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法第81条
第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
労働基準法第75条
第1項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
第2項
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
もう一歩前へ ~解雇権濫用法理との関係~
そもそも使用者が従業員を解雇しようとする場合、解雇に合理的な理由があり、当該解雇が社会通念上相当といえることが必要です。これを解雇権濫用法理(労働契約法16条)といいます。
参照:解雇について
そして、業務起因性のある傷病を負った労働者を解雇する場合にも、当然、解雇権濫用法理は働きます。
したがって、不合理又は相当性を欠く解雇は、解雇権濫用法理(労契法16条)に反し無効です。
では、会社が「打切補償」を行った場合はどうでしょうか。1200日分の手当てを補償が支払った場合においても、解雇権濫用法理は適用されるのでしょうか。
解雇権濫用法理(労契法16条の)適用はある。
まず、原則として、解雇権濫用法理は適用されます。
解雇権濫用法理は解雇一般に適用されるからです。労基法19条も、打切補償の場面で、労働契約法16条の適用を排除する体裁・形式にはなっていません。
ただし、機能する場面は限定的
もっとも、その一方で、打切補償がなされているとの事実を、解雇権行使の合理性・相当性を基礎づける事実の一つとして評価することは可能です。
また、法が、傷病によって一定期間休業した労働者の解雇につき、打切補償を条件に、19条1項本文の解雇制限の解除を認めていることを斟酌すれば、打切補償の場面では、解雇権濫用法理の適用を限定的・抑制的にすべきとの考えも成り立ち得ます。
裁判例においても、打切補償がなされた場合においては、会社が、業務上の疾病の回復のための配慮を全く欠いていた等の特段の事情がない限り、解雇の合理性・相当性が認められるとするものがあります(平成22年9月16日東京高裁判決等)。
打切補償がなされた場面においては、解雇権濫用法理により解雇が無効とされる場面が限定される傾向にあると考え得ます。