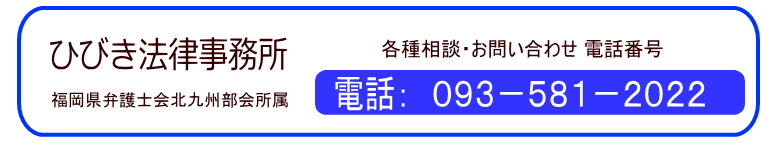労働時間は、労使ともに関心の深い労働条件の一つであり、労働基準法において、労働時間法制ともいうべき各種制度が整備されています。
労働時間は、労使ともに関心の深い労働条件の一つであり、労働基準法において、労働時間法制ともいうべき各種制度が整備されています。
また、当該企業において、どのような労働時間制度が採用されているかは、労働者の働き方や残業代の算定にも大きな影響を及ぼします。
そこで、本記事では、原則的な労働時間法制を確認したうえで、変形労働時間制等、その他の特別の制度を俯瞰します。
原則的な労働時間
労働基準法は、原則的な労働時間の上限を、1日8時間、週40時間と定めています。
使用者は、この労働時間を超えて労働者に労働をさせるには、法律上の一定の条件を満たす必要があり、また、その場合には、使用者は労働者に対して、残業代を支払わなければなりません。
参照:残業代について
労働時間の算定は、実労働時間を通算して算定するのが原則です。
たとえば、朝9時から午後6時までの勤務時間の内、お昼休みに1時間の休憩がある場合、労働時間は、午前9時から午後12時まで3時間と、午後1時から午後6時までの5時間とで合計8時間となります。
<補足>
なお、労働時間に関係するルールとして、休憩、休日に関するルールがあります。
まず、労働者に6時間を超える労働をさせる場合には労働時間に応じて一定の休憩を与える必要があります。
また、労働者には、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与える必要があります。
原則的な労働時間制度に関する特別のルール
上記の通り、労働基準法は、原則的な労働時間の上限を、1日8時間、週40時間と定めています。これは労働時間の枠組みに関するルールです(ルール①)。
また、労働基準法上、労働時間の算定は、実労働時間を通算して行うのが原則となります。これは、労働時間の算定方法に関するルールです(ルール②)
他方、労働基準法は上記ルール①及びルール②について、次のような制度を設け、労働時間制度の柔軟化を図っています。
<労働時間の枠組み(ルール①)に関する特別な制度>
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
<労働時間の算定方法(ルール②)に関する特別な制度>
・労働時間のみなし制
・裁量労働制
労働時間の枠組み(ルール①)に関する特別な制度
に関する特別な制度.jpg) 原則的な労働時間の枠組み(ルール① 1日8時間、週40時間)に関して、その緩和・解除を認める労働基準法が認める特別の制度が、変形労働時間制及びフレックスタイム制です。
原則的な労働時間の枠組み(ルール① 1日8時間、週40時間)に関して、その緩和・解除を認める労働基準法が認める特別の制度が、変形労働時間制及びフレックスタイム制です。
以下、変形労働時間制及びフレックスタイム制の順に見ていきます。
なお、こうした制度の採用は残業代の算定に大きな影響を及ぼします。
変形労働時間制
変形労働時間制は、一定の単位(1年、1月、1週の3つの単位がある)の期間について、1週間当たりの労働時間数の平均が40時間の枠内に収まっている場合に、特定の日ないし期間において、1日8時間、1週40時間の法定労働時間の規制を解除ないし緩和しうる制度です。
変形労働時間制の下では、閑散期の労働時間を短くする反面、繁忙期の労働時間を1日10時間とする等の制度設計が想定されます。
たとえば、1年単位の変形労働時間制の下、1日の労働時間を10時間、1週の労働時間を50時間と定めた期間においては、労働者が1日10時間、週5日労働しても残業代は付加されません
この期間において残業代が付加されるのは、たとえば、労働者が1日12時間働いた場合(2時間分の残業代の付加が必要)や労働者が週に50時間を超えて働いた場合です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)における総労働時間を定め、労働者に始業・修業時刻の決定を労働者にゆだねる仕組みです。
この制度は、労働者に対して柔軟な働き方を認めることにより、労働者の「働きやすさ」を確保しやすい、という点にメリットがあるといわれています。
フレックスタイム制の下では、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えた労働がなされた場合に、残業代が必要となります
たとえば、清算期間をひと月とするフレックスタイム制の下では、次の総枠を超える労働が行われた場合に使用者は労働者に対して残業代を支払う義務を負います。
| 清算期間 | 法定労働時間の総枠 |
| 31日の場合 | 177.1 時間 |
| 30日の場合 | 171.4 時間 |
| 29日の場合 | 165.7 時間 |
| 28日の場合 | 160.0 時間 |
労働時間の算定(ルール①)に関する特別な制度
 原則的な労働時間の算定方法(ルール② 実労働時間を通算ルールが原則)に関しても、労働基準法は、特別の算定方法を定めています。事業外労働のみなし制と裁量労働制です。
原則的な労働時間の算定方法(ルール② 実労働時間を通算ルールが原則)に関しても、労働基準法は、特別の算定方法を定めています。事業外労働のみなし制と裁量労働制です。
以下、時間外労働のみなし制と裁量労働制の順に見ていきます。
※ その他、坑内労働にも特別のルールがありますが割愛します。
事業外労働のみなし制とは
事業外労働のみなし制というのは、次の仕組みを認める制度です。
- 労働者が、労働時間の全部または一部について事業外で業務に従事し、かつ、労働時間の算定が困難な場合には所定労働時間だけ労働したものとみなす。
- 但し、その業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる労働をしたものとみなす。
この事業外労働のみなし制というのは、営業職が外回りで仕事をする場合や、労働者が出張する場合など、労働者が事業所外で労務を行うために、労働時間の算定が困難な場合に、労働者が、一定の時間、労働をしたとみなす仕組みです。
一定の場合には、在宅勤務の労働時間も、この仕組みを用いて労働時間を算定することが可能とされています。
裁量労働制
裁量労働制というのは、労働者が、その業務の性質上、大きな裁量をもって労働をしている場合に、一定の条件の下で、所定の時間だけ労働者が働いたとみなす制度です。
システムコンサルタントや弁護士、公認会計士等が専門職労働者として業務を行う場合(専門業務型裁量労働制)や、事業の企画・立案・調査・分析に関わる業務を労働者が行う場合(企画型裁量労働制)などが想定されています。
裁量労働制は、専門業務型裁量労働者、企画型裁量労働者が労働時間の規制になじみにくいことを根拠とします。
適用除外について
以上、原則的な労働時間法制の他、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、裁量労働制を俯瞰してきました。通常の労働者は、これらの仕組みの枠内で、労働を行うことになります。
ただ、上記とは別に、労働基準法は、一定労働者につき、労働時間、休憩、休日に関する規制を適用していないこととしていますので、最後に、労働基準法の労働時間等に関する規制が適用されない労働者を紹介しておきます。
- 農業・畜産・水産業に従事する労働者
- 管理監督者及び機密事務取扱者
- 関し・継続的労働従事者(主務官庁の許可を得た者に限る)
上記の内、特に問題となるのは、②の管理監督者です。ある労働者がこの管理監督者に該当する場合には、労働時間の規制が及ばず、残業代も発生しません。
したがって、ある労働者が管理監督者に該当するかは、労使ともに大きな関心事となります。
この「管理監督者」をめぐっては、判例による解釈も積み重なっていますので、別の機会に解説します。