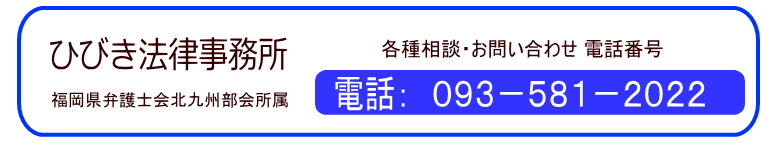建物建築工事において、建物屋根がスレートの場合、常に踏み抜きの危険が付きまといます。今回はスレート踏み抜き事故に関する裁判例を二つ紹介します。
労働安全衛生法に基づく義務
特に高所作業については、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置する、作業床を設置することも困難な場合には、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる必要があります。
これは、労働安全衛生法によるルールです。
民法における安全配慮義務
他方で、労災事故が発生した場合、事業者が、上記の内、一つでも行っていれば、十分かというと必ずしもそうではありません。
事業者は、当該工事現場の実情に応じた転落防止措置を講ずるなど、労働者の安全に対し配慮する義務を負います。
民事裁判ではこの安全配慮義務を事業者側が尽くしたか否かが争点となります。
裁判例
以下、二つ裁判例を紹介します。
富山地方裁判所高岡支部昭和61年6月24日
スレート踏み抜き事故に関する裁判例として紹介する一つ目は、富山地方裁判所高岡支部昭和61年6月24日です。
この裁判例の事案は、被災者が、工事の管理運営を任された責任者であり、被災者自身につき、「工事が安全に遂行されるよう配慮すべき職務上の義務があった」とされた事案です。
裁判所は次のとおり判示して、安全配慮義務違反を肯定しました。具体的事例の下、事業者側に高度の安全配慮義務を課しています。
【判示】
右のとおり、被災者Sはスレート工事の管理運営を任されていた責任者の立場にあった者であるから、工事が安全に遂行されるよう配慮すべき職務上の義務があったものというべきであり、この点、Sは本件工事につき格別の安全対策を講じなかった点で手落ちがあったことは否めないが、しかし、だからと言って、雇用主である被告のSに対する労働契約に基づく安全配慮義務を負うことを否定することはできない。
なお、営業所には命綱が備えられていて、Sは本件工事に際してもこれを用意していたことが窺われ、Sが命綱の端を確実に固定し、かつ、正しくこれを着装していたならば、同人がスレート葺屋根を踏み抜いても宙吊りになるだけで、床に墜落死亡することはなかったものと考えられなくはない(もっとも、命綱の端を確実に固定することが容易であったかどうか疑問があるが)。
しかしながら、事業主は、前記安全配慮義務に基づき、従業員に多少の過誤があっても事故が生じないよう万全を尽くすべき義務があるところ、被告は右義務に基づき本件工事現場に前記認定の踏み抜きによる墜落防止措置を講ずべきであったにもかかわらず、右義務に違反し、その措置を講じなかったものであるから、仮に、Sにおいて本件事故につき右過失があったにしても、被告は、本件事故につきその責を免れるものではない。
東京地判昭和28年5月31日判決
併せて、東京地判昭和28年5月31日判決を紹介します。この事案は、事業者の安全配慮義務違反を肯定した上で、労働者が、安全帯を親綱に掛ける等の措置を全く講ずることなく、漫然と本件スレート屋根に上がったと認定して2割の過失相殺をした事案です。次のように判示しています。
【安全配慮義務違反について】
スレート葺きの屋根に上がる作業を行う際には、踏み抜きによる落下事故の発生する危険が生ずることが明らかである。
したがって、当該落下事故の発生を防止するため、当該作業に従事する者の安全帯を親綱に掛けさせ、さらに、当該屋根に上がる際には、その支柱等の上を移動させる等の配慮が必要となると考えられる。
しかしながら、上記(1)において認定したとおり、Bは、安全帯に親綱を通していない状態のAに対し、本件スレート屋根上に登ってはならない旨の特段の注意をすることもなく、陸屋根の上に垂れ下がり、又は本件スレート屋根に引っ掛かった状態の親綱を本件スレート屋根に上げるように指示し、しかも、全ての親綱を本件スレート屋根の上に上げる作業が終わる前に、Aの動静に注意を向けることもなく、自らの作業をしていたというのである。
このような本件事故の発生時における状況に鑑みると、破産会社においてAに対する安全配慮義務を尽くしていたものということはできず、その結果、本件事故が発生したものといわざるをえない。
【過失相殺について】
本件スレート屋根に上がる場合に踏み抜きによる落下の危険が生ずることはAにとっても予見することが可能であったものということができるところ、安全帯を親綱に掛ける等の措置を全く講ずることなく、漫然と本件スレート屋根に上がったことが本件事故の発生に起因したことは否めない。
そうすると、Aには相応の過失を認めることができるというべきところ、上記において認定し、及び説示した本件事故の発生時における状況等に鑑みると、その過失相殺の割合は、2割と認めるのが相当である。