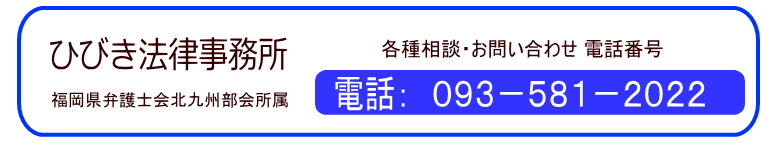当事者
原告:管理組合(区分所有法3条前段)の理事長
被告:社会福祉法人
居宅介護支援事業等の公益事業を行うことにより高齢者や障害者に対する福祉サービスを提供することを目的とする。本件マンションの区分所有者から本件住戸を賃借して占有。
時系列
| 日時 | 当事者 | 内容 |
| H28 | 消防署→原告 | 消防署から原告に被告入居の住戸には自動火災報知設備が必要との指導。 |
| H28.6.1
(1度目の通知) |
原告→被告 | 原告は、被告に対し、被告が本件マンションにおいて福祉施設を運営することは管理規約12条1項に違反するとして、H29.5.31までに退去するよう求めた。 |
| H28.7.7 | 被告→原告 | 被告は、原告に対し、被告による使用態様は管理規約12条1項に違反せず、退去しない旨を通知。 |
| H28.11.19 | 管理組合 | 管理組合は、通常総会を開催し、管理規約に「専有部分を民泊に供することの禁止(管理規約12条の2)」、「専有部分をシェアハウスに供することの禁止(同12条の3)」、「専有部分をグループホームに供することの禁止(同12条の4)」、「専有部分を特定防火対象物となる用途に供することの禁止(同12条の5)」を追加することを議案として審議した。審議の結果、上記議案は4分の3以上の賛成により可決。 |
| H29.6.21
(2度目の通知) |
原告→被告 | 原告は、被告に対し、被告入居の住居の使用を停止することを求める。 |
| H29.7.6 | 被告→原告 | 被告は、原告に対し、本件使用は管理規約に違反しないとして、原告の要求に応じない旨を通知。 |
| H30.4.21 | 管理組合 | 管理組合は、臨時総会を開催。
議案:共同利益背反行為の停止請求訴訟に関する件 議題①:被告に対して本件住居をグループホームとして使用する行為の停止を求める訴訟の提起 議題②:弁護士費用等の訴訟に必要な費用を請求する訴訟の提起 →賛成組合員数168名、賛成議決数182個 反対組合員数3名、反対議決権数3個 棄権組合員数4名、棄権議決権数4個 ⇒過半数の賛成で可決(以下「本件決議」。) |
| H30.6.14 | 原告→被告 | 本件訴訟を提起。 |
争点
争点1:被告が本件各住戸をグループホームとして使用することが本件管理規約12条1項に違反する行為であるかいなか。具体的には、本件管理規約12条1項「住宅」の解釈及び被告の占有態様が「住宅」としての使用にあたるかいなかが争点である。
争点2:本件管理規約12条の4及び12条の5の各規定が無効であるかいなか(判断されなかった)。
争点3:被告が本件各住戸をグループホームとして使用することが、区分所有法6条3項により準用される区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかどうか。
争点4:本件管理組合の被告に対するグループホーム事業の停止請求及び本件決議が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)8条1項の「不当な差別的取扱い」及び障害者基本法4条1項の「障害を理由」とする「差別」に該当し、違法無効であるかどうか。
争点5:被告が本件管理規約68条2項に基づき負担する費用及びその額。
前提事実(マンション等の建物の防火設備について)
以下、前提事実を説明します。
(1) 防火対象物の定期点検報告について
消防法施行例別表に定めてある防火対象物にあたると、管理権者は、1年に1回、防火対象物点検資格者に当該防火対象物について、消防法等が規定する事項について基準に適合するか検査させ、その結果を消防署・消防署長に報告しなければならない(消防法8条の2の2第1項、消防法施行規則4条の2の4第1項、同施行規則4条の2の6、平成14年消防庁告示第12号)。
グループホーム利用前の本件マンションは、消防法施行例別表に定めてある防火対象物にあたらなかった。しかし、グループホーム利用開始後の本件マンションは前記防火対象物にあたる。本件マンションの検査は、約51万円かかる。
(2) 消防用設備について
複合用途防火対象物にあたると、消防用設備等の設置義務を負う(消防法17条、消防法施行令6条)。もっとも、この設置義務は、消防庁等が、消防設備等の基準によらなくとも火災の発生や延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めた場合(これを大阪市では「共同住宅特例」という。)に限り、緩和される(消防法施行令32条)。
本件マンションは、複合用途防火対象物である。そのため、管理組合は、本件マンションをグループホームとして利用しているか否かにかかわらず、原則として、消防用設備等の設置義務を負う。もっとも、本件マンションは、グループホームとしての利用開始後であっても、共同住宅特例の①共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50%以上であること、②住戸利用施設の床面積が合計1000㎡未満であること、③住戸利用施設の核独立部分の床面積がいずれも100㎡以下であることという要件を満たしており、消防用設備の設置義務を免れている。
当事者の主張(要約)
以下、当事者の主張を紹介します。
争点1
まず、被告が本件各住戸をグループホームとして使用することが本件管理規約12条1項に違反する行為であるか否かについてです。。
①本件管理規約12条1項の「住宅」をどのように判断するのかについて
| 原告の主張(主張立証責任を負う) | 被告の主張 |
| 区分所有法30条1項に基づき規定された管理規約12条1項の目的からすると、「住宅」にあたるか否かを判断するためには居住用建物としての平穏さだけでなく管理組合の業務等に及ぼす影響も考慮すべきである。
|
本件各住戸の使用が本件管理規約12条1項の「住宅」としての使用であるか否かは,本件各住戸が入居者の生活の本拠であるかいなかによって判断されるべきである。 |
| 本件管理組合が消防関係法令に基づき本件マンションに消防設備等を設置しなければならないか否かは,被告が本件各住戸を本件管理規約12条1項所定の「住宅」として使用しているかいなかとは無関係である。 |
②被告のグループホームとしての使用は「住宅」としての使用にあたるかいなかについて
| 原告の主張(主張立証責任を負う) | 被告の主張 |
| 本件マンションは建設当初から大阪市の共同住宅特例の適用のあるマンションとして分譲されている。そのため、グループホームが入居することにより共同住宅特例の適用が除外されることは管理組合の業務に重大な影響を及ぼす。
|
知的障害者が隔離収容されてきた歴史的経緯からすると、障害者グループホームは、普通の環境の中で地域住民としての生活を送るため、普通の住宅であることが求められている。そして、本件グループホームは、住宅としての使用と異なるところはない。そして、グループホームの入居者の利用実態としても、生活の本拠としても住居としての利用である。 |
| 本件グループホーム事業のように起臥寝食する場として提供されている場合、消防関係法令により、住宅以上の防火対策を講じなければならない。また、グループホームは、グループホーム利用者の安全性を確保するために大阪府の条例による設置基準に従い開設・運営している施設である。これらのようなグループホームの性質・特性からしても、グループホームとしての使用は「住宅」としての使用にあたらない。 |
争点2について
本件管理規約12条の4及び12条の5の各規定が無効であるか否かについては省略。
争点3について
被告が本件各住戸をグループホームとして使用することが、区分所有法6条3項により準用される区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかいなか。
| 原告の主張(主張立証責任を負う) | 被告の主張 |
| 本件マンションにおいて「共同住宅特例」が適用除外されると、管理組合は多額の費用を投じて防火設備を設置する必要があり、その費用を捻出するためには修繕積立金を取り崩したり、区分所有者から一時金を徴収したりしなければならなくなる。
本件マンションにおいて「共同住宅特例」が適用除外されなくても、適用除外されたときに管理組合が上記の対応をとらなければならないというリスクを排除することが、区部所有者の共同の利益に資する。 |
障害者がグループホームに入居することは、障害のない者がマンションの住居に入居することと同じである。
障害者のグループホームにおける生活は、近隣住民の平穏な生活を害することはない。 本件グループホームの入居者により、過去にトラブルを生じさせたこともない。
|
| 共同住宅特例が適用されていても、管理組合は防災措置に関する業務を行わなければならなくなる。今後、グループホームを運営する事業者が増えた場合、管理組合は避難契約や消防計画を策定しなければならなくなり、これらはグループホームとして使用することにより生じる負担である。 | 消防関係法令の改正により、マンションにおいて障害者グループホームが存続でき、かつ他の区分所有に負担が生じないように規制の修正がなされた。そのため、本件マンションの区分所有者に現実的な負担は生じていない。 |
| 本件マンションは、被告のグループホームとしての利用により、非特定防火対象物から特定防火対象物に変更になった。本件マンションが特定防火対象物になることにより、管理組合は、消防法に基づき防火対象物定期報告をしなければならなくなった。 | 本件マンションは、消防法施行令の関係上、各住戸に消防用設備等の設置は義務付けられていない(スプリンクラー等の設置はグループホームとして利用している部屋のみ)。
防火対象物点検についても,令和2年12月23日の消防法施行規則の改正により,点検の範囲は,障害者グループホームとして使用されている本件各住戸内と本件各住戸から1階屋外までの避難経路の点検のみで十分である。 |
| 本件マンションにおいては共同住宅特例の適用が除外されていない。また、共同住宅特例の要件に照らすと、共同住宅特例の適用除外になる現実的可能性は低い。 | |
| 管理費の増加に関しても、防火対象物点検は、本件各住戸内及びその避難経路の書類による点検のみで足りるから、大きな負担ではない。また、当該防火対象点検は被告の責任をもって行う。管理組合は、以前から消防用設備等の点検を実施しており、慣れているから、大きな影響はない。
管理組合が防火対象物点検を行うことは、防火安全性を向上させるものであり、本件マンション全体の利益に資する。 |
争点4について
本件管理組合の被告に対するグループホーム事業の停止請求及び本件決議が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)8条1項の「不当な差別的取扱い」及び障害者基本法4条1項の「障害を理由」とする「差別」に該当し、違法無効であるかどうか(省略)
争点5について
被告が本件管理規約68条2項に基づき負担する費用及びその額(省略)
裁判所の判断(詳細は別紙2の判決参照)
以下、裁判所の判断についてです。
(1) 争点1の管理規約12条1項の「住宅」の解釈について
| 規範 | 「区分所有者又は占有者が専有部分を住宅として使用しているというためには,住宅としての平穏さが確保される態様,即ち生活の本拠として使用しているとともに,その客観的な使用の態様が,本件管理規約で予定されている建物又は敷地若しくは附属施設の管理の範囲内であることを要すると解する」 |
| 理由 | ①管理規約は区分所有法30条1項に基づき定められたものであり、規約12条に「住宅」として使用する旨の記載がある。
②住宅以外の用に供されると、建物等の管理について負担が増加し、共同の利益が損なわれるおそれがある。 |
(2) 争点1の被告の占有は住宅としての使用にあたるかについて
| 結論 | 「被告は,被告との間で指定共同生活介護サービス利用契約を締結した利用者の生活の本拠として本件各住戸を使用しているが,その客観的な使用の態様は,本件管理規約で予定されている建物又は敷地若しくは附属施設の管理の範囲外のものと認められる。被告が本件各住戸をグループホームとして使用することは,本件管理規約12条1項の規定に違反する行為に該当する。」 |
| 理由 | ①被告が本件マンションをグループホームとして使用することにより管理組合は防火対象物点検義務を負うようになるところ、管理規約には本件マンションが特定防火対象物となる用途に供されることを前提とする火災の予防等の対策を定めた規定はないから、防火対象物点検義務は管理規約に予定されている管理の範囲外である。
②被告が本件マンションをグループホームとして使用することにより、本件マンションは共同住宅特例の適用を維持するための対応を余儀なくされる・共同住宅特例の要件に適合しなくなる危険を負担することなるところ、管理規約に福祉施設等が存在することを許容する規定はないから、共同住宅特例の要件に適合しなく危険を負担するのは管理規約に予定されている管理の範囲外である。 |
(3) 争点3(被告のグループホームとしての使用が「共同の利益に反する行為」にあたるかいなかについて)
| 規範 | 「区分所有者の共同の利益に反する行為に該当するかどうかは,当該行為の必要性の程度,これによって他の区分所有者が被る不利益の態様,程度等の諸般の事情を比較考量して決すべきものであると解する。」「本件管理規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互の利害調整のための共通規範として制定されたものである(区分所有法30条参照)から,本件管理規約に違反する行為は,共同の利益に反する行為に該当するか否かの考慮要素として重視されるべき」 | ||
| あてはめ | グループホームとして使用する必要性 | グループホームとして使用することにより他の区分所有者が被る不利益 | 裁判所の判断
|
| 被告が本件各住戸で営む障害者グループホーム事業は,障害を有する利用者に共同生活の場所を提供するという公益性の高い事業。 | 不利益①:点検定期報告について
管理組合は、本件マンションにつき防火対象物点検義務を負い、その費用は年間51万8400円かかる。 不利益②:消防設備について 共同住宅特例が適用されなくなった場合、管理組合は消防用水・消火活動に必要な施設を設置し、維持しなければならないという経済的負担がある。 共同住宅特例が適用されていても、管理組合は、共同住宅特例の適用がなくなった場合に備えて検討を続けなければならない。 |
被告が本件管理規約12条1項の規定に違反して本件各住戸において事業を営むことによる利益が、他の区分所有者が被る不利益よりも優先されるとは認められない。なお,被告は,本件マンション以外のマンション等においてもグループホームを経営していることが認められるから、被告が本件各住戸以外の建物においてグループホームを経営することができないとはいえない。 | |
(4) 争点4・5(省略)
共同の利益についての判断についての検討
大阪地判令和4年1月20日判決について
ア 特徴
一般的に、「共同の利益」(区分所有法6条1項)に反する類型として、不当毀損行為・不当使用行為・ニューサンス行為・不当外観変更行為等が挙げられます[1]。
下記の裁判例をみると、共用部分の毀損や専用部分の規約外利用等の行為そのものを共同の利益に反する根拠にしています。それらの裁判例に比べ、本判決は、グループホームとしての利用自体を契機として訴訟まで発展しましたが、グループホームとしての利用それ自体というより、グループホームとしての利用による管理費用の増加及び将来における管理組合の対応の負担を共同の利益に反する根拠としました。本判決は、占有者の専有部分の利用態様そのものではなく、利用に伴う管理の負担増加を共同の利益に反する根拠として点が特徴を有すると考えられます。
イ 考えられる本判決の射程
前述の通り、本判決は、消防法の諸規定から防火対象物の定期点検報告費用の増加及び防火設備設置の可能性による将来の管理組合の不利益を根拠に区分所有法6条1項の共同の利益に反するとしています。
本判決が、消防法の諸規定から本件マンションの管理費用増加及び防火設備設置の可能性による将来の管理組合の不利益を重視しているのであれば、グループホームと同様に消防法施行例別表に防火対象物として挙げられている救護施設・乳児院・障害児入所施設・障害者支援施設・老人デイサービスセンター・こども園等にもマンションの管理費用増加及び防火設備設置の可能性による将来の管理組合の不利益という根拠はあてはまるため、本判決の射程は前記列挙した施設にも及ぶのではないでしょうか。
ウ 判決を読んでいての疑問
本判決は、将来において生じるかもしれない不利益を認定し、共同の利益違反を導いています。これらの不利益は、将来生じるかどうかも分からない一般的・抽象的不利益ともいえるため、共同の利益に反すると判断する根拠にしてもいいのでしょうか。それとも、反対に、将来の不利益を根拠としてはならないと規定がない以上、判断の材料にするのは裁判官の自由心証の範囲内といっていいのしょうか。
[1] 稻本洋之助=鎌野邦樹『コンメンタールマンション区分所有法〔3版〕』(2015)日本評論社p45-50.
丸山英氣 「区分所有法」信山社(2020)p421-424